情動・情緒の発達を支援につなげるためのポイントとは?
子どもの「気持ち」をどのように捉えていますか?
なかでも障害を持つ子の「気持ち」は?
障害児への支援では「気持ち」というキーワードが使われることが多いです。
気持ちを大切にしよう。
気持ちを表出しよう。
支援目標でよく見かけます。
では、どうやってそれらを評価すればよいのでしょうか?
また、気持ちの発達とはどのようなものなのでしょうか?
今回は気持ち(「情緒」「情動」)の発達を説明します。
情動と情緒の違いは?
情緒?情動?なんだ?と思う方もいると思います。
両方とも「気持ち」のことです。
障害が重い子と「情動」「情緒」
障害が重い子、発達が初期段階の子は「情動」や「情緒」に問題が起きることがあります。
ここでいう問題とは気持ちが崩れやすい等の不安定さを指します。
たとえば下記のような要因があります。
理解することができない
周囲で起きていることが分からない状況です。
発達初期の子は自分の周りにある情報を受け取ることが上手ではありません。
・聞こえてくる音の意味が分からない
・大人が何かしようとしてくれているが意図が分からない
・看板に描かれているものの意味が分からない
周囲で起こっている物事の意味が分からなければ不安になります。
さらに自分の気持ちも相手に伝えられない子が多い。
そのため発達初期の子は不安定になりやすいのです。
上手く伝えられない
ことばが出ていない子は少なくありません。
喋れたとしてもうまく自分の気持ちや状況を相手に伝えられない子もいます。
肢体不自由の子の場合、身振りやサインも難しい子もいます。
生理的要因がある
生理的要因とは自分では何とかすることが難しい状況を指します。
過敏という問題があります。
過敏とはちょっとの刺激でも耐えられないくらいに感じてしまうことです。
そういった問題があると気持ちは不安定になってしまいます。
外から聞こえる機械音が耐えられないくらい嫌。
他のことは考えられなくなる。
過敏は「聴覚過敏」だけではありません。
すべての感覚器(視覚、聴覚、触覚、味覚など)に起こる可能性があります。
「ちょうどよい」が難しい
得意でない状況では不安定になりやすいということが分かりました。
では、穏やかに楽しい環境で過ごしてもらえばよいのでしょうか?
このくらいなら楽しめるという幅を把握しておくことは大切です。
しかし、盛り上げるばかりの支援は逆効果なのです。
楽し過ぎて崩れてしまう
発達初期段階の子は、楽しくなり過ぎて気持ちが崩れることがあります。
「子どもが喜んでいるから」といって、次から次に盛り上げてしまう。
子どもを楽しませ続ける「過剰な盛り上げ」の支援をする人もいます。
ちょうどいい「楽しい」をオーバーしてしまうと、いままで笑顔だったのに突然泣き出してしまいます。
訳が分からなくなってしまうのです。
これが混乱です。
これでは、せっかく楽しんだのに支援者も子どもも報われません。
適度な「楽しい」で遊んでもらう。障害児保育の重要な視点です。
このような「情緒」と「情動」を発達と結び付けている支援方法や理論はいくつかあります。
なかでも分かりやすいのが「感覚と運動の高次理論」です。
感覚と運動の高次化理論とは?
感覚と運動の高次化理論とは障害を持つ子の発達をみるための方法です。
健常児の発達から障害児を見ていくものではありません。
障害があるがゆえに発達的な課題につまづいてしまう。
そんな障害児特有の発達の凸凹をとらえていくものです。
気持ちの問題も根底には感覚や身体の不安定さがあります。
発達にはそれぞれ前提となる力が存在します。
対人関係が苦手な子に対して、繰り返し対人関係の練習をする必要はありません。
それよりも
・相手に意識を向ける
・一緒に何かができる
などのことを遊びを通して練習していくことが大切なのです。
それらが対人関係の育ちに貢献するといわれています。
◆詳しくはこちらの記事もどうぞ
情動の発達と対応
分かっているようで捉えにくい「気持ちの発達」支援。
情動とはどのように育っていくのでしょうか?
まずは障害を持つ子の情緒の特徴を復習しましょう。
いっきに育つのではなく少しずつ進んでいくイメージです。
① 発達初期の子が反応に乏しいわけ
発達が初期段階の子は自分や他者、ものに感情が向くことがありません。
反応が乏しいように見えてしまうことがあるのはそのためです。
「心地よい」「気持ちが悪い」といった「快・不快」を感じたとしても拒否がほとんどみられません。
② 周囲に意識が向くようになる
光や声などの周囲からの刺激に少しずつ気がづくようになってきます。
このような「感覚刺激」は自分以外に意識を向けるキッカケとなります。
「感覚刺激」は外からの大切な情報です。
危険や心地よさ以外にも「楽しさ」や「自分が何をすればいいのか?」といったことが分かるようになってくるのです。
この「気づき」が知恵の育ちに貢献するのです。
③ 好き嫌いが出はじめる
知恵の育ちが進んでいくと「好き」「嫌い」が分かってきます。
嫌いなものは明確に拒否するようになってきます。
これを選択的拒否といったりします。
④ 情緒が不安定になってくる
「気づき」によって外に目が向くようになってきました。
自分にとって好きなもの・嫌いなものにも気付くようになりました。
しかし、世界はそう単純ではありません。
まだまだ複雑で理解しきれないことが山ほどあります。
自分から他者に伝える手段(伝達手段)もまだ乏しいです。
このような状況から情緒がさらに不安定になることがあります。
発達が進んだために不安定になったという状況です。
**********
こちらの記事もどうぞ
まとめとして
今回は「気持ち」も発達について説明しました。
気持ちを専門用語でいうと「情緒」もしくは「情動」です。
「情緒」は自分の中で起きた原因による「気持ち」。
「情動」は周囲の人やものが原因で起きた「気持ち」。
「気持ち」の発達をみるときは何となく担ってしまいがちです。
「情緒」や「情動」という視点を持ってみると子どもをより深く見ることができるはずです。
良かったら参考にしてみてくださいね。
<参考文献>
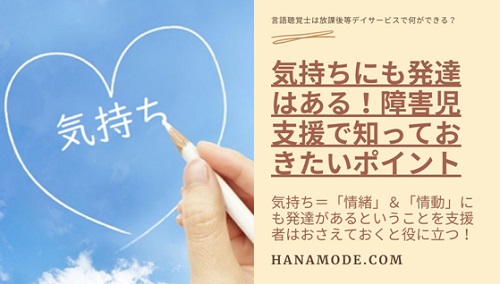


![障害児の発達臨床(1) 感覚と運動の高次化からみた子ども理解 [ 宇佐川浩 ] 障害児の発達臨床(1) 感覚と運動の高次化からみた子ども理解 [ 宇佐川浩 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7614/76140704.jpg?_ex=128x128)
![障害児の発達臨床(2) 感覚と運動の高次化による発達臨床の実際 [ 宇佐川浩 ] 障害児の発達臨床(2) 感覚と運動の高次化による発達臨床の実際 [ 宇佐川浩 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7614/76140705.jpg?_ex=128x128)