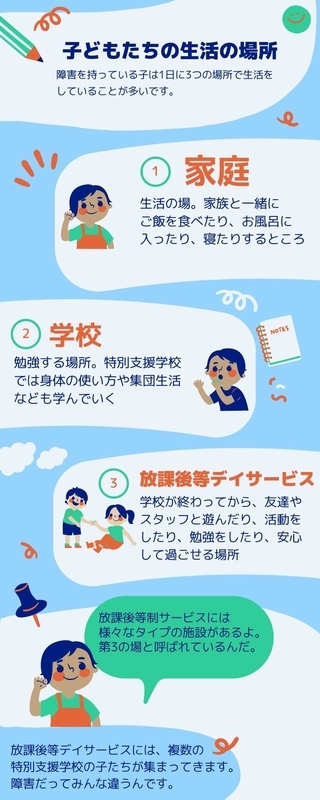これから放課後等デイサービスで働く新人STがまず考えたほうがよいこと
新しく放課後等デイサービスで働きはじめた言語聴覚士(ST)は、いろいろ悩むことも多いと思います。
その中のひとつ「何から学べばいい?」という話しです。
周囲からの期待も大きいはず。
しかし、何をすればよいのか分からず焦る日々・・・。
わたしも国家資格を取ってからわずか数年で放課後等デイサービスで働き始めました。
もちろん一人職場でした。
だれも「STがやるべきこと」なんて教えてくれません。
そんななかで「こうしておけばよかった」というはなしをしたいと思います。
改めて「小児」の言語聴覚士について考えてみる
言語聴覚士は「聞こえ」「飲み込み」「ことば」を対象としたリハビリ職 / コメディカルです。
具体的にいうと、
◆聞こえ
→聴覚障害の子に対する訓練・指導、聴能訓練、補聴器・人工内耳の調整・指導などです
◆飲み込み
→摂食嚥下障害を持つ子への訓練・支援
◆ことば
→ことばに遅れがみられる子への訓練・指導。何らかの原因でことばが出ない子、出づらい子への支援などです。
放課後等デイサービスとは何か?
最近、名前を聞くようになってきた放課後等デイサービス。
放課後等デイサービスが求人票に載っているのをよく見かけます。
ではいったい放課後等デイサービスとはどのようなところなのでしょうか?
第3の場所としての居場所
家族から「放課後等デイサービスってどんなところなの?」と聞かれたら答えられますか?
放課後等デイサービスについて改めて確認しましょう。
子どもにとって「第三の場」である放課後等デイサービス。
障害を持った子の「塾」ではありません。
働き始めてからおさえておきたいポイント
障害児分野では言語聴覚士の需要は高いです。
場所を選ばなけらば、ほぼ100%就職できます。
問題は入職してから。
養成校では、あまり小児分野は勉強していないし、実習で小児施設に行けなかったという人も多いと思います。
「何をすれば良いのか分からない」
「何から勉強していけばいいの?」
そう感じているはずです。
しかし、ポイントさえ押さえておけば大丈夫です!
ポイントは次の通りです。
① 一緒に働いている職種(職業)を知ること
放課後等デイサービスには様々な職種のスタッフが参加しています。
そのため、他職種がどのようなことを考えているのかを知ることが大事です。
まずは放課後等デイサービスの柱として働いている、保育職の考え方について学んでいくとよいです。
実際に保育スタッフから教えてもらうのもよし、本から学ぶのもよし。
基本的に保育職は子どもの気持ちを大切にしていて、それに寄り添う形で支援を進めていくことが多いです。
言語聴覚士の養成校では習わなかった視点ですね。
おすすめの本は

- 価格: 2200 円
- 楽天で詳細を見る
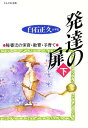
- 価格: 2200 円
- 楽天で詳細を見る
「保育」という立場から子どもの発達について書かれています。
言語聴覚士とは異なる視点でもあるので勉強になります。
② 子どもは自分の思い通りには動かないこと
経験の浅いSTが勘違いしやすいこと。
「大人の言うことを聞かせるのが正しい支援だ!」
そう思い込みやすいのです。
冷静に考えてみると明らかに間違っていますよね。
子どもにどのように関わっていきたいのか?
それは常に頭の隅に置いておきたい考え方です。
③ STは「治す」仕事ではないこと
障害がある子を治してあげる。
喋るようにしてあげる。
経験の浅いSTで勘違いしている人が多い点です。
こんな姿勢で子どもに接してもうまくいきません。
周囲からの反感も買います。
いずれ自分自身がその職場で働きづらくなりますよ。
注意したいポイントです。
子どもに対する考え方のポイント
放課後等デイサービスでは小学校1年~高校3年までの最長12年間、ひとりの子どもをみることもあります。
なんとなく接していると、あっという間に卒業していってしまいます。
そうならないためにも、子どもを把握するときのポイントを紹介します。
あくまで「最初はこういう風に見た方がいいよ」というポイントです。
まずは子どものパターンを押さえよう
おすすめは、実際に子どもと接しながら、その子の行動パターンを覚えることです。
障害児と言っても、まったく同じ子はいません。
ひとりひとり性格も違えば反応の仕方や行動パターンも異なるのです。
教科書通りの子どもはほとんどいない
子どものパターンとは、
・決まった歌が聞こえると笑う
・Yesのときに片方の口角だけ動く
・特定の場面で耳を塞ぐ
・楽しくなり過ぎた後には必ず泣く
など、たくさんあります。
これらに対して支援者が「何でだろう?」と思うことで、ようやく支援のスタートラインに立ったといえます。
「この障害には、この療法を行う」が鉄則ではないの?
そう思っている人も多いでしょう。
しかし「○○障害」という教科書通りの症状の子は、わりと少ないです。
そのため、
今どのような状態なのか?
どのような発達をたどっているのか?
と考えてアプローチを決めていくことが大切です。
「どうして?」を大切にする
子どもの言動や反応をみて、
・なぜできたのだろう?
・なぜできなかったのだろう?
と考えることが大切です。
・こういう嗜好がある
・こういう発達段階だからだ
・発達に凸凹があるな
子どもに対する「なぜ?」「どうして?」を施設で使っている理論や療法に当てはめて考えていきます。
施設で決められた理論や療法がないところもあります。
その場合は自分の好きな(というか信じられる)療法をみつけましょう。
おすすめは
・インリアル
・感覚と運動の高次化理論
・モンテッソーリ
まとめとして
今回は、これから放課後等デイサービスで働きたい言語聴覚士、経験の浅い言語聴覚士へ「子どもと関わるときにはどのように考えればいいのか?」を説明しました。
国家資格を取ったばかりだと少々天狗になりやすいです。
実はわたしもそうでした。
それでたくさん失敗しました。
そうならないためにも、楽しく働くためにも、「STが一番ではない」ことを忘れないでください。
周囲の職種に助けられて、はじめて輝くことができる職種なのです。
そこから仕事が面白くなってきますよ。
よかったら参考にしてみてくださいね。
あわせて読みたい
www.hana-mode.com