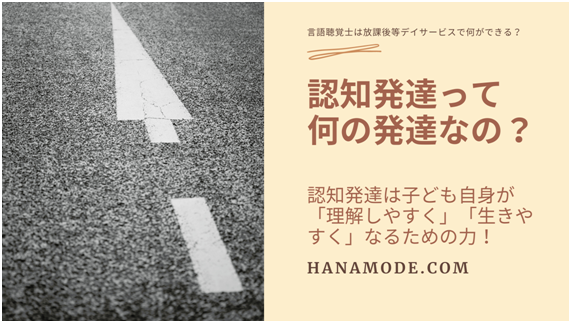認知発達とは何なのか?
障害児や教育の分野でよく耳にする「認知発達」。
動きやことばと違って分かりにくい発達の種類です。
今回は認知発達はどのようなもので、どんな流れで獲得していくのか?という説明をしていきます。
認知とは
「認知」とは
感じ取ったものが
・どんなもの?
・どんな価値があるもの?
・自分はどうすればいい?
を理解して行動に移すまでの一連の流れ のことです。発達の骨組み(中核)となる力。「知恵」「知的」といわれることもあります。
外から得た情報をしっかりと受け取って「自分が何をすればよいのか?」判断する。それによって、さらに高度な力を身につけられるようになってくる。そのような一連の流れが「認知発達」なのです。
認知するまでの流れ
① 感覚刺激
⇒ 外からの刺激が入ってくる
② 感知
⇒ 「何か手に当たった」と気づく
手だけではなく、見える(目)、聞こえる(耳)の場合もある
③ 知覚
⇒ 「手に当たったのは丸くて硬いものだ」
過去の経験などと照らし合わせて形や大きさなどを感じとること。完治したものが「どんなものか」大体で感じ取ること
④ 認知
⇒ 「手に当たったのはリンゴだ」
自分の中の知識と照らし合わせて「それは何なのか」を判断、認識すること。また、その価値を判断することともいえる
いろんな意味を持つことば「認知」
「認知」は分野によって様々な使われ方をします。
・障害児、教育分野
⇒ 認知発達という意味
・高齢者福祉の分野
⇒ 認知症という意味
・社会分野
⇒ 自分の子だと認めること
※この記事では、障害児・教育分野の「認知発達」について説明していきます。
認知発達の種類
「認知」とは、周囲にあるものを感じ取って、その意味を把握することだと分かりました。
意味を把握できれば「次に何をすべきか」が分かるようになります。その積み重ねが子どもの「発達」「育ち」なのです。
認知発達にはたくさんの種類があります。
右に行くにしたがって高度な力になります。
認知はどのように育つのか?
いろんな種類がある認知発達。
ではどのように発達は進んでいくのでしょうか?
認知発達はコミュニケーション発達にも影響する
周囲からの刺激や自分の周りで起きたことを把握するということは「ことば」や「コミュニケーション(対人関係)」の発達にも影響を与えます。
たとえば、
目の前にいる人が「指さし」や「何かの身振り」をしたとします。
しかし、これらの意図することが分からないと、相手が何を言いたいのか分かりません。
コミュニケーションとは相手の意図をくんで返すことです。
このように「理解出ないからコミュニケーションできない」というケースもあるのです。
「認知発達」と「コミュニケーション発達」。別物なんじゃないの?
そう思われるかもしれません。しかし認知発達は別の発達にも影響を与えるのです!
認知の力を使うともっと高度な力を獲得できる
認知発達では、育つ過程で様々な力を身につけていくことになります。
・目や耳の使い方
・記憶
・模倣する力
・複雑なことを簡単に捉える力(概念)
・様々な事柄をことばなどに置き換える力(象徴)
1つ獲得するとパワーアップして、もっと難しいことができるようになるのです。それはロールプレイングのようなゲームに似ています。
模倣についてはこちらの記事をどうぞ
まとめとして
今回は認知発達について説明しました。
認知発達は育っていく過程で、より高度な力を獲得するために必要となるシステムのことです。
子どもは日々自分自身をアップデートしながら育っていくのです。
それが結果的に「生きやすく」なり、自分自身を助けることになるのです。
参考資料